1. はじめに:高配当株は“毎月のご褒美”をつくる投資
正直、最初は配当利回りの数字しか見えてなかった。5%って聞くと「お、なんか得じゃん」って思うよね。でも実際は、利回りは“入口の数字”でしかない。大事なのは、その配当が来年も、その次の年も続くかどうか。ここを外すと、せっかく買ったのに「減配」でトータル負け…というのがよくある落とし穴。
このページでは、昔の自分に向けて「最短で失敗しにくい型」をまとめた。むずかしい専門用語は最小限。チェックするポイントだけ絞って、“今日から組める”配当ポートフォリオを作っていこう。
この記事でわかること
- 初心者でも迷わない銘柄の選び方(5つの必須チェック)
- おすすめ銘柄リスト(国内/米国/ETF/J-REITをバランスよく)
- 10万円からの積み上げプランと“買う日”のルール
- NISAと税金の超要点(深追いしないでOKな範囲)
- よくある失敗と回避法、そして保有後のメンテ方法
先に伝えておく“リアルな話”
- 高配当株は一発逆転の投資じゃない。コツコツ積み上げて、配当を“仕組み化”する投資。
- 「利回りランキングの上位=勝ち組」ではない。配当性向・キャッシュフロー・財務を見ないと事故る。
- 生活を良くするのは“配当額の増加”で、含み損益の増減じゃない。だから配当が続く会社を選ぶのが最優先。
この先の読み方(サクッと時短)
- 次章で選定基準の5チェックだけ掴む
- 「結論:おすすめ銘柄」に飛んで候補をざっと把握
- 「10万円からの積み上げ」を読んで自分の買い方に落とす
- 保有後は「メンテ方法」を半年〜年1回見直しに使う
リスクも正直に
- 減配リスク:景気後退・投資負担で配当が削られることは普通にある
- セクター偏り:商社・リート・エネルギーなどに寄り過ぎるとブレが大きい
- 金利・為替:米国株は為替次第で配当の体感が変わる(円高時は買い場にもなる)
大丈夫。チェックポイントを固定して、買い方をテンプレ化すれば、“毎月なにかしら入る”配当スケジュールは作れる。次章で、銘柄を選ぶ前に絶対おさえたい5つの必須チェックをサクッと共有するね。

2. おすすめ銘柄の“選定基準”
配当って、「会社が稼いだお金の一部を株主におすそ分け」だよね。
大事なのは“今年だけじゃなく、来年・再来年もそのおすそ分けが続くか”。
この“続くか”を確かめるために、下の3つだけ覚えればOK。
まずはここを見よう
A) 利回りは高すぎない?
- 目安:国内3〜5%/米国2.5〜4.5%
- 例えると:ケーキのサイズ(利回り)が“やたらデカい”ときは、スポンジ(会社の稼ぐ力)がスカスカなことが多い。
- どう見る?:「なんでこんなに高い?」を一言で説明できるか(特別配当?株価が落ちた?)。
B) おすそ分けの“取り分”は無理してない?(=配当性向)
- 目安:30〜70%が無理なく続けやすい。
- 家計で言うと:「給料のうち、どれくらいをお小遣いに回してるか」。お小遣いが多すぎると、ちょっと残業減っただけで生活が苦しくなる=減配しやすい。
C) 現金はちゃんと入ってる?(=キャッシュフロー)
- 目安:本業の現金収入(営業CF)が安定、余ったお金(フリーCF)がプラスだと安心。
- 家計で言うと:「毎月の給料が安定して、家賃やスマホ代を払っても余りが出てる」。余りがあるから“お小遣い(配当)”が続く。
ここだけでだいたい7割は判断できる。
余裕があれば次の“応用2点”も足すとズレにくい。
慣れてきたら足す
D) これまでちゃんと配ってきた?(=配当履歴)
- 目安:5年以上の増配 or 減らしてない。
- 家計で言うと:「ボーナスが少ない年でも、家族に渡すお小遣いを急にゼロにしない家」。
E) 体力はある?借金だらけじゃない?(=財務)
- 目安:自己資本比率40%以上、借金の重さ(有利子負債/EBITDA)3倍未満が理想。
- 家計で言うと:「ローンが年収に対して重すぎない」。金利が上がると返済がキツく ⇒ お小遣い(配当)が削られる。
よくある落とし穴
- “利回り7〜8%だから勝ち”:見かけが大きいだけ。来年小さくなる(減配)+株価下落のダブルパンチになりがち。
- 特別配当:今年の“臨時ボーナス”。来年の給料(平常配当)は変わらない=当てにしすぎない。
- 投資の出費が重い時期:新工場や大型買収の直後は余り(フリーCF)が細る。成功ならOKだけど、減配の可能性も上がる。
- 同じ業界に偏る:景気が悪くなると同時に痛むから、配当がグラつきやすい。
書類のどこを見ればいいの?
- 決算短信(サマリー):配当方針・今期の配当予想
- 決算説明資料(スライド):事業の見通し・“配当を続ける根拠”が言語化されてることが多い
- キャッシュ・フロー計算書:
- 営業CF(給料)
- 投資CF(大きな出費)
- フリーCF=営業CF−投資CF(毎月の“余り”)
覚え方:利益より“現金”を見る。黒字でも現金が足りないと、配当は続かない。
同じ“利回り5%”でも結果が変わるミニ物語
- A社:給料が毎年安定、家賃や通信費を払っても余りが出る、ローンも軽い、ここ5年お小遣いは毎年少しずつ増やしてきた。
→ 来年も同じくらいのお小遣いが期待しやすい。 - B社:給料はブレが大きい、出費が重くて毎月赤字気味、ローンはずっしり。
→ 今年はお小遣い多めでも、来年は減らす(減配)確率が高い。
用語ミニ辞書
- 配当利回り:株価に対して、1年でもらえる配当の割合。
- 配当性向:利益のうち、配当に回す割合(家計の“お小遣い比率”)。
- 営業CF:本業で現金がどれだけ入ったか(毎月の“手取り”)。
- フリーCF:手取りから大きな出費を引いた“余り”。配当の原資。
- 自己資本比率:自分のお金の厚み。厚いほど不景気に耐える。
- 有利子負債/EBITDA:借金の重さを年収で割った感じ。小さいほど楽。
- 連続増配:毎年配当を少しずつでも増やし続けていること。
- 特別配当:今年限りの臨時ボーナス。来年もあるとは限らない。
最後に:実際の選び方は“順番ゲー”
- 利回りが常識的な帯にいるか
- 配当性向が無理じゃないか
- 現金(営業CF/フリーCF)が回ってるか
- 配当を守ってきた文化があるか
- 体力(財務)があるか
→ OKが多いものから“主力”に、△が混じるものは“サブ”に回す。OKが少なければ“見送り”。
3. まずは分散設計:ETF+主力2〜4社+配当“月”の並べ方
やることはシンプル。
①土台(ETF)→②主力(個別)→③配当月の穴埋めの順で置いていく。それだけ。
3-1. 土台=ETFを1本置く
- なぜ?
個別株は当たり外れがある。ETFは“かたまり”で持つから、ひと社の減配で全体が崩れにくい。 - 何を選ぶ?
「高配当ETF」を1本。国内でも米国でもOK(為替の影響はあるけど分散の価値が勝ちやすい)。 - 買い方
給料日に自動で毎月固定額。ここは“何があっても買う”レーンにする。 - 効果
株価が上下しても配当が浮いてくる。メンタルが折れにくくなる。
まずはここに全体の30〜40%。初心者は“多め”でもOK。
目的は「続けられる土台づくり」。
3-2. 主力=個別株を2〜4社だけ(生活インフラ目線)
- なぜ?
個別は“性格の違い”を楽しめる。とはいえ多すぎると見られない。
はじめは2〜4社で十分。 - どう選ぶ?
キーワードは「役割が消えない会社」。
例:電気・通信・生活必需・医薬・インフラ・リースなど。
(前章の“やさしい基準”で、A/B/Cの3点チェックを通すだけでも精度が上がる) - 置き方
ETFの次に各社に少額ずつ。慣れたら主力を増やすより買い増しで厚みを出す。
主力ブロックに40〜50%。
“ETF多め/個別少なめ”が最初はラク。
3-3. 配当“月”を並べる
- なぜ?
日本株は3・6・9・12月に偏りがち。空白の月が続くとやる気が切れる。
米国株・海外ETFを混ぜるとほぼ毎月になる。 - やり方
スマホのカレンダーに配当月を書き込む。空いてる月に“もう1社/ETF”を置く。 - 効果
入金メールが定期的に来るから、再投資の回転が上がる。
まずは「3・6・9・12」をETFで埋め、
次に空いてる月(例:1・4・7・10、2・5・8・11)を主力でじわっと埋める。
3-4. “買う日”のルールは2本立て
- 定期買い(機械):ETFは毎月固定額。
- ちょい押し追加(手動):主力は25日移動平均−5%前後で1単位買い増し、を“ゆるルール”に。あくまで一例。
チャートの完璧さは不要。トリガーがあることが大事。
今月は給料が多く入ったから少し買おう、このくらいの気持ちでOK
これだけで“天井掴み”が減って、平均買付単価が落ち着く。
3-5. 待機資金(暴落の味方)をあらかじめ分ける
- なぜ?
すべて投資してしまうと、下げ相場で動けなくなる。 - 目安
年初に10〜20%を“暴落用”として別口座へ。普段は触らない。 - 効果
下げ相場で買いに行ける。結果、のちの配当利回りが押し上がる。
3-6. 最初の10万円を置いてみる(例)
- ETF:4万円(土台・毎月積立)
- 主力A:2万円(通信/公益など)
- 主力B:2万円(生活必需/医薬など)
- 主力C:1万円(景気敏感の優等生)
- 待機資金:1万円(“押し目で1単位”の種)
翌月以降もETFに自動で1万円、主力は押し目で薄く足す。
「毎月の固定+たまの追加」のリズムを固定化。
3-7. メンテは“触りすぎない”(半年〜年1回でOK)
- どこだけ見る?
①配当方針が変わっていないか
②本業の現金(営業CF)がやせてないか
③セクターの偏り(同じ種類ばかりになってない?) - 迷ったら:まず新規買いを止める。いきなり売らない。
“理由がはっきりしたら縮小”の順。
3-8. 失敗しやすいパターンを先回りで潰す
- 利回り順でかき集める → 入金が3/9に集中、他の月が空白→継続が難しくなる。
- 主力を増やしすぎる → 10〜15社は見きれない。最初は2〜4社。
- 全部を一気に買う → 暴落用の弾がない。待機資金を最初に分ける。
4. 【結論】おすすめ高配当“候補”リスト
まずは“土台=ETF”→“主力=個別”の順。ETFは分散された配当をまとめて受け取れるので、はじめての人でも続けやすい。
高配当ETF(土台づくり)
1) iシェアーズ MSCIジャパン高配当 ETF(東証:1478)
- なぜ候補?
MSCIのスクリーニングで“配当と財務健全性”を同時に見た日本株バスケット。東証上場&新NISA成長投資枠でも使える土台枠。 - どう使う?
毎月の自動積立で“入金の芯”に。国内だけで組みたい人のスタート地点。 - 注意点
インデックスの入れ替えでセクター構成が変わることがある(年次の見直しで点検)。モーニングスターの評価も参考材料。
2) 上場インデックスファンド日本高配当(東証:1698)
- なぜ候補?
TSE Dividend Focus 100を追う“日本の高配当100”型。構成がわかりやすく、国内だけで完結させやすい。 - どう使う?
1478とどちらか一方でOK。国内コアの“1本目”。 - 注意点
組入銘柄が高配当寄りに偏るぶん、相場次第で価格変動はある。最新の概況は適宜チェック。
3) Vanguard VYM(米:VYM)
- なぜ候補?
FTSE High Dividend Yield Indexを追う米国の定番。広く分散しつつ高配当ゾーンを拾う“王道”ETF。 - どう使う?
為替影響は受けるが、配当“月”の穴埋めに最適(米ETFは分配がズレやすい)。 - 注意点
米国課税×日本課税の二重課税はNISA/特定口座の扱いも含めて記事後半で解説推奨。
4) Schwab SCHD(米:SCHD)
- なぜ候補?
“配当の質”にフォーカスした指数を採用。財務指標でふるい、持続しやすい配当を狙う設計。2025年の年次入替でエネルギー比率が上がった点は特徴。 - どう使う?
VYMとどちらか1本。より“質”寄りの米配当を足したいとき。 - 注意点
セクター偏り(エネルギー比率上昇)には性に合う/合わないがあるので好みで。
個別株(主力候補・日本株中心)
個別は2〜4社から。ここでは「役割が消えにくい」&「配当方針が明確」の代表例を置くよ。
5) KDDI(9433)— 通信のコア、累進配当で“配当文化”が太い
- なぜ候補?
20年以上の連続配当成長。2024年度は23期連続増配を達成、2025年度もさらに増配目標を明記。通信は需要がぶれにくく、配当政策も一貫。 - どう使う?
“生活インフラ枠”の1枚目に。米ETFと合わせると配当月のズレも作りやすい。 - 注意点
規制・価格競争のニュースで株価は動く。年1回の方針確認を忘れずに。
6) 東京ガス(9531)— エネルギーの安定配当+緩やかな増配方針
- なぜ候補?
「安定配当+緩やかな増配」を掲げ、2025年3月期は配当予想を年間80円に上方修正。自己株買いも併用し、株主還元の明確化が進行。 - どう使う?
配当の“安定源”としてコアに。 - 注意点
LNG価格や政策の影響は受ける。原料市況の急変が続く局面では慎重に。
7) オリックス(8591)— 事業分散×配当+自社株買いの還元設計
- なぜ候補?
2025年3月期の配当性向39%、翌期も「39%または年間120.01円の高い方」という“ルール明記型”。分散事業で景気の波をならす。 - どう使う?
金融・リース枠の中核。配当+買い戻しの総還元を取りに行くイメージ。 - 注意点
投資回収のタイミングで利益が上下する局面あり。年次でCFの手触りを確認。
8) 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)— 配当性向“約40%”方針
- なぜ候補?
「配当性向40%程度+安定的な増配」を基本政策に明記。2025年3月期は年64円の見通しを開示(※時点情報)。金利環境の変化で利益体質が改善している点も追い風。 - どう使う?
金融枠の定番。国内だけのポートでも配当のベースを作りやすい。 - 注意点
市況次第で含み損益(有価証券)や海外与信が効く。四半期ごとに一言チェック。
9) 三井物産(8031)— 連続増配を伴う株主還元の強化(商社の代表例)
- なぜ候補?
2025年度も年間100円配当の方針を開示。さらに柔軟な買い戻しも継続。商社は資源サイクルに左右されるが、近年はバランスよい還元ポリシーが定着。 - どう使う?
いわゆる景気敏感枠。ポートに“息吹”を与えるピース。 - 注意点
資源価格のサイクルで配当継続性が左右される。ピークで追わないこと。
(補足)米個別は“無理に入れなくてOK”
米個別なら生活必需品(例:P&G)や公益など“役割が消えにくい”領域が王道。ただし言語・税制・情報量のハードルがあるので、はじめのうちはVYM/SCHDで十分だよ。
どう組む?(ぱっと置ける並べ方)
- 土台(ETF):1478または1698のどちらか1本+VYMかSCHDのどちらか1本
- 主力(個別):KDDI+東京ガス+(オリックス or MUFG or 三井物産)から2〜3社
- 配当“月”:カレンダーに入れて、空いている月に米ETFを足すと“毎月なにか入る”形に近づく
※銘柄は“候補”。最終的には前章の「やさしい5チェック」(利回り帯/性向/CF/履歴/体力)で1社ずつ判定を。
5. 具体例:10万円からの積み上げ
例として「初期10万円」は、スタート時に一度だけ用意する“土台づくり”の費用です。いったん土台を置いたら、その後は家計に合わせて積立でOK。つまり、最初に10万円を置き、その後は少額をコツコツ積み立てる――この二段構えで進めます。
最初の10万円は、土台→主力→待機資金の順で置いていく。やることは3つだけ。
5-1. はじめの10万円、こう置く
- ETF(土台):4万円
→ 「毎月の入金」を作る基礎。積立予約までその場で設定。 - 主力(個別):5万円(2〜3社に分ける)
→ 生活インフラ系から2社、景気敏感を入れるなら薄く1社。 - 待機資金:1万円
→ 押し目用。別口座/サブ口座に分けて“見えない化”。
目的:翌月から自動で進むレーンを先に確定させてしまうこと。思考より、先に“予約”。
5-2. 翌月から:毎月の“台本”
- 給料日に自動発射
- ETFに1万円の積立(金額は家計に合わせてOK)
- カレンダーで空白月を埋める
- 今月の配当が薄い月なら、主力のうち空白月に配当が来る銘柄を1単位だけ追加
- ちょい押し拾い(あれば)
- これは一例だけど、主力が25日線から▲5%前後なら、待機資金から5,000〜1万円だけ買い増し
自分のルールを作ってOK
- これは一例だけど、主力が25日線から▲5%前後なら、待機資金から5,000〜1万円だけ買い増し
これで「固定」と「状況対応」の二刀流になる。完璧な底は狙わなくていい。“買うタイミング”を自分で作るのが大事。
5-3. 配当“月”の並べ方
- 日本株は3・6・9・12に偏りやすい。
- 米ETF(VYM/SCHDなど)は3・6・9・12以外も分配が入る。
- まずは日本株+国内ETFで3/6/9/12を埋め、空いた1/4/7/10や2/5/8/11に米ETFを置くと、ほぼ毎月“なにか入る”形になる。
入金メールが月1回でも来るだけで、継続力が段違い。心理面の“ご褒美設計”だと思ってOK。
5-4. “買う日”のゆるルール 例
- 固定:ETFは毎月の金額をいじらない(家計が苦しい月でも止めない額に設定)
- 追加:主力は「25日線−5%で1単位」のサインが出たら、深呼吸→買う
- 暴落時:相場全体が−10〜−20%のときは、待機資金から等分で3回に割って入れる(“一撃”はしない)
ルールを紙に書いてスマホメモに固定。迷ったら“ルールに従う”でOK。
5-5. どれくらい増える?
- 例:初期10万円+毎月1万円積立、平均利回り3.5%想定
- 1年目の受取配当(税前):約8,000円前後
- 3年継続で、入金の回数が増え、再投資の回転数が上がる
- 価格が下がる年は、再投資の効率が上がる年でもある(配当再投資の“うま味”)
ポイントは金額より「止めずに回り続ける仕組み」。複利は“回転数”で効き始める。
5-6. NISAの使い分け
- 成長投資枠:高配当ETF/個別のメイン置き場。再投資の邪魔になる税金を避けやすい。
- 特定口座:NISA枠が埋まったらこちら。外国税額控除(米配当)などは確定申告の“やる/やらない”で決める。
- 再投資 or 使う?:
- 目標が“将来のゆとり”なら再投資>生活費
- ただし、気持ちが続くご褒美として“月1回の小額使い”を決めておくのはむしろアリ
迷ったら:「いまは土台を大きくする時期か?」「もう配当で生活を少し楽にする時期か?」を自問。
5-7. 半年〜年1回の点検
- 見るのは3つだけ
- 会社の配当方針が変わっていないか(累進配当/性向の文言)
- 営業CF→FCFがやせてないか(大出費期でも3年平均でプラ転見込みか)
- セクター偏り(同じタイプに寄りすぎてない?)
- “うーん”と思ったら:新規買いを一旦停止。理由がはっきりしたら縮小。総入れ替えはしない。
6. 税金&NISAのポイント
配当を“育てる”なら、置き場所の順番だけ最初に決めておくと迷いません。基本は、非課税=NISAを優先、枠が足りない分は特定口座(源泉あり)で受ける。この並べ方にしておけば、税金まわりでつまずきにくいです。
6-1. 置き場所の順番
- ① NISA・成長投資枠
配当と売却益が枠内で非課税。再投資にブレーキがかかりにくい=雪だるまを転がしやすい。 - ② 特定口座(源泉あり)
税の計算と納付を証券会社が自動処理。手間が少ないから続けやすい。
結論:高配当=成長投資枠へ。枠が埋まったら特定(源泉あり)でOK。
6-2. NISAで“できる/できない”
高配当の個別株・ETF・REITはNISAで持てる(多くが成長投資枠)。一方、“積立用の投資信託”はつみたて投資枠の出番。
- できる:個別株/ETF/REIT(=高配当の主戦場)
- 注意:枠は有限。土台(ETF)を優先し、主力は2〜4社に絞るとムダ打ちが減る
6-3. 海外配当と“二重課税”の考え方
米国株や米ETFの配当は、現地(米国)で先に税が引かれるのが普通。NISA口座でも日本側は非課税だけど、現地分は基本そのままです。
- 初心者の運用指針
まずはNISAで育てる → 慣れてきたら外国税額控除(確定申告)を検討でも遅くない - 割り切り方
「非課税の恩恵で回転数(再投資頻度)を上げる」ほうが、序盤は効きやすい
6-4. NISAと特定口座の使い分け
NISAの成長投資枠に土台ETF+主力2〜4社を置いて、あふれた分は特定(源泉あり)に“待避”。
- NISA:土台(高配当ETF)→主力(2〜4社)
- 特定(源泉あり):NISAで入りきらない分の置き場(自動で納税まで終わる)
6-5. 配当の受取と再投資
配当は口座に現金で入る設定にしておくと、次の買付に回しやすいです。やることは2つだけ。
- ETF:毎月の自動積立をオン(配当も“勝手に再投資”の動線に乗る)
- 個別株:配当月の空白を埋める形で少額を買い足す(5,000〜1万円)
ワンアクション:配当が入った日に、次の買付メモを1行(銘柄/金額/日付)。迷いが消えます。
6-6. よくある勘違い
- 「NISAなら海外配当も全部非課税だよね?」
→ 日本側は非課税。でも現地で引かれる分は基本そのまま。 - 「特定口座は難しそう」
→ 源泉ありを選べば何もしなくてOK(自動で計算・納税)。 - 「配当は全部使っちゃダメ?」
→ 目的次第。増やす時期は再投資>生活費、ただし“ご褒美の少額”はむしろ継続に効く。
7. よくある失敗と回避
7-1. 利回りだけで選ぶ
- ありがち:ランキング上位(7〜8%)に飛びつく → 翌年減配+株価も下落。
- なぜ起きる?:利回りは“結果の数字”。株価下落や一時要因で見かけが膨らんでるだけのことが多い。
- 回避:まずは利回り帯/配当性向/フリーCFを確認。
- ワンフレーズ:「来年も再来年も、その配当が続く根拠は?(現金の余りで払える?)」
7-2. 配当“月”の空白を放置して続かない
- ありがち:3・9月に偏って、他の月は“ゼロ”が続いてやる気が切れる。
- なぜ起きる?:日本株だけで組むと四半期偏重になりがち。
- 回避:国内ETF+米ETFを混ぜて、空白の月に小さく1社足す。
- ワンフレーズ:「毎月、何かしら入ってくる形に寄せる=継続の燃料。」
7-3. 主力を増やしすぎて管理不能
- ありがち:10〜15社になって、結局どれも見られない。
- なぜ起きる?:“分散=銘柄数”と考えてしまう。
- 回避:ETFを土台にして、個別は2〜4社に絞る。厚みは買い増しで。
- ワンフレーズ:「広くはETF、深さは個別で出す。」
7-4. 暴落時に動けない(フルインベスト)
- ありがち:常に全額投資 → 下げた時に何もできない。
- 回避:年初に待機資金10〜20%を別口座へ。全体−10〜−20%で3回に分けて投入。
- ワンフレーズ:「現金は“怖さ”を和らげる安全装置。」
7-5. “ニュースで心が揺れて”ルール崩壊
- ありがち:減配の噂、景気悪化の見出しで衝動売買。
- 回避:半年〜年1回の点検日を決め、見るのは配当方針/営業CF→FCF/偏りの3点だけ。
- ワンフレーズ:「“いつ”見るかを決めたら、それ以外では見ない。」
7-6. 為替を無視して米配当を評価
- ありがち:円高局面で米配当が目減り → 期待外れに感じる。
- 回避:円・ドルを両方持つ前提で、短期の為替は“揺れ”として扱う。
- ワンフレーズ:「為替は“風”。家(配当設計)の柱は動かさない。」
失敗を避ける“最短チェック”
- 利回りは常識的な帯(国内3〜5%、米国2.5〜4.5%)か
- 配当性向30〜70%/フリーCFプラスの手触りがあるか
- 配当月の空白を放置していないか(毎月に近づける)
- 個別は2〜4社に絞れているか(ETFが土台になっているか)
- 待機資金は別口座で10〜20%キープできているか
8. メンテナンスのやり方(半年〜年1回でOK)
配当投資は「触りすぎない」が基本。でも見るべき3点は固定しておくとブレません。
点検日はあらかじめカレンダーに“年2回”入れておくと、ニュースに振り回されにくくなります。
8-1. 企業ごとの「3点チェック」
- 配当方針:累進配当・配当性向の文言に変更なし?
- 現金の手触り:営業CFがやせていない? 3年平均でFCFがプラス圏?
- 無理の兆候:配当性向が80%付近に張り付き始めていない?
ひと言メモ(1行でOK):「配当方針◎/FCF△/性向○=様子見」など。
メモが溜まるほど、売買判断の迷いが消えます。
8-2. ポートフォリオ全体の「3点チェック」
- 偏り:セクター・国・配当“月”が一方向に寄っていない?
- 重さ:1銘柄の比率が20%超になっていない?(超えたら“利食い”候補に)
- 待機資金:口座に10〜20%残っている?(暴落時の安全装置)
8-3. 行動ルール(停止→縮小→入替の順)
- 新規買いを停止:
- 配当性向が高止まり(80%前後)
- FCFマイナスが連続/大型投資期で先の見通しが弱い
- 縮小(部分売却):
- 減配を発表し、翌期の回復シナリオが不明確
- 1銘柄比率が20%超でポートが脆い
- 入替:
- 累進配当撤回など方針が根本的に変化
- 10年目線で“役割が薄れた”と判断できるとき
いきなり総入れ替えはしない。「停止→縮小→入替」を数週間〜数ヶ月で段階的に。
8-4. RAG(赤黄緑)ミニ判定表
| 指標 | 緑(維持) | 黄(注意) | 赤(対応) |
|---|---|---|---|
| 配当性向 | 30–70% | 70–85% | 85–100%超(恒常化) |
| FCF(営業CF−投資CF) | プラス維持 | 年一時マイナス/改善見込みあり | 連続マイナス/改善根拠薄 |
| 配当方針 | 累進・維持明記 | 文言あいまい/未更新 | 累進撤回・減配示唆 |
| 連続増配/安定 | 5年以上継続 | 一度据置/微減 | 直近減配・無配化 |
| 財務(有利子負債/EBITDA) | <3.0倍 | 3.0–4.0倍 | >4.0倍(上昇基調) |
| 自己資本比率 | ≧40% | 30–40% | <30%(低下基調) |
| セクター/比率偏り | 1銘柄≦20% | 20–25% | >25%(集中) |
| 見通し(会社ガイダンス) | 保守的でも増益/横ばい | 不透明・レンジ広め | 明確な減益+投資負担増 |
判定ルール:一番厳しい色が全体判定。例:性向“緑”、FCF“黄”、方針“赤”なら赤。
- 緑(維持):性向30〜70%/FCFプラス/方針堅持/比率20%以下
- 黄(注意):性向70〜85%/FCF一時マイナス/大型投資期/比率20%超
- 赤(対応):減配発表/性向>90%継続/方針後退/FCFマイナス連続
数字が多少ズレてもOK。大事なのは“傾向”。
黄判定は“次の決算までの宿題”にして、メモを1行残すと迷いが減ります。
赤に振れたら比率を先に落とす(売り切らなくていい)。土台ETFや別の緑銘柄に置換。
黄は“新規停止+観察”、赤は“縮小/入替”の検討へ。
9. まとめ&次の一歩
配当投資は“当てる”ゲームではなく、続ける仕組みを作るゲーム。
土台(ETF)→主力2〜4社→配当月の空白を埋めるの順で置き、
NISAの成長投資枠を優先に、年2回の3点チェックだけで淡々と回す。
悩んだら「利益より“現金”(営業CF/FCF)を見る」に立ち返れば大きく外しません。
今日のアクション
- 高配当ETFを1本決めて、毎月5,000〜1万円の積立を予約
- 主力を2社だけ選び、少額で“試し置き”
- カレンダーに点検日(半年後)を登録、RAG表をブクマ
おすすめ証券口座




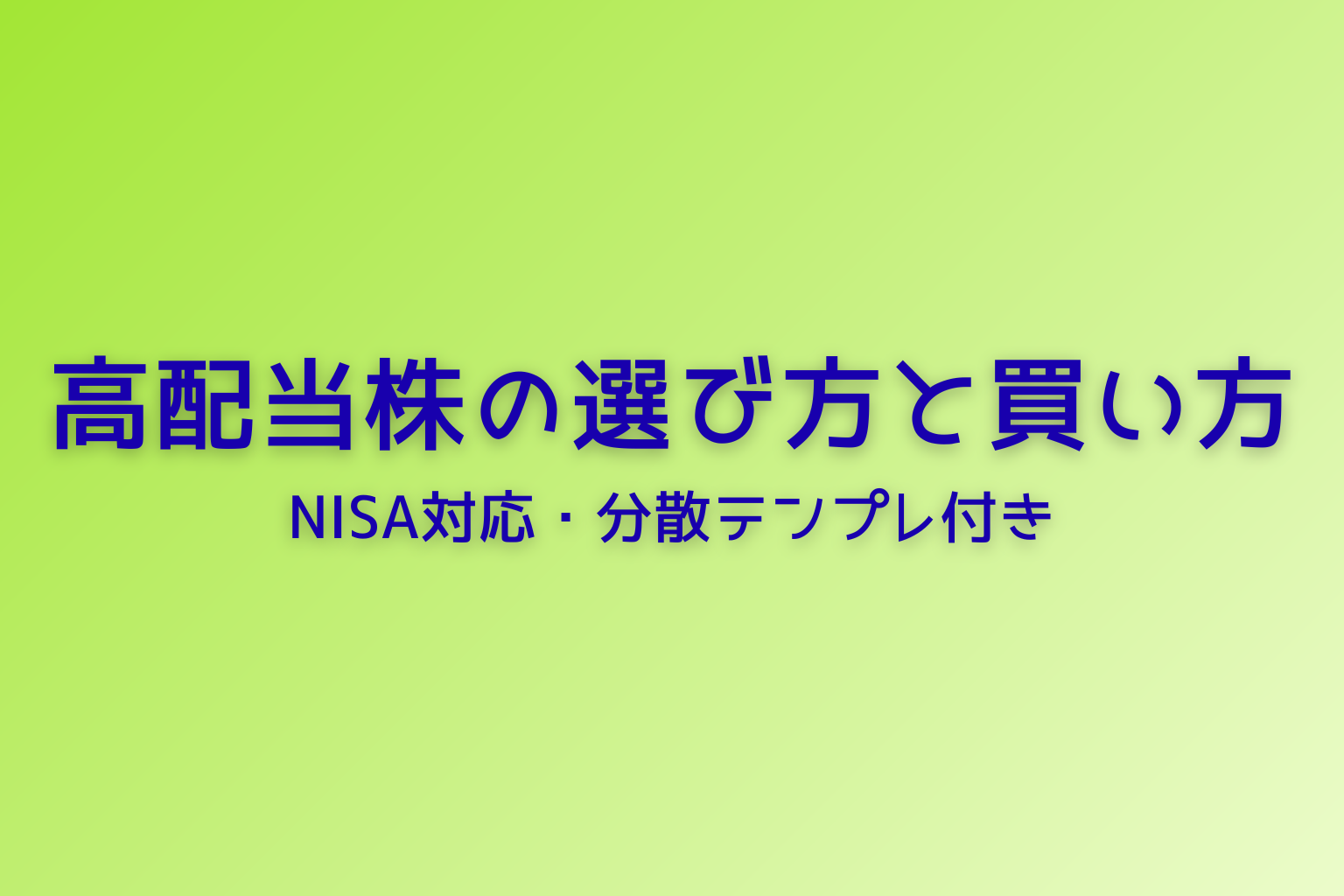
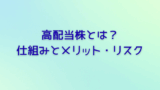
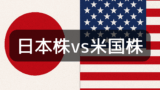

とは?-120x68.png)
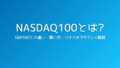
コメント